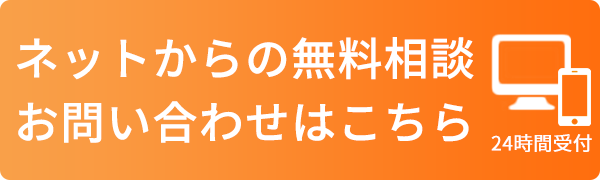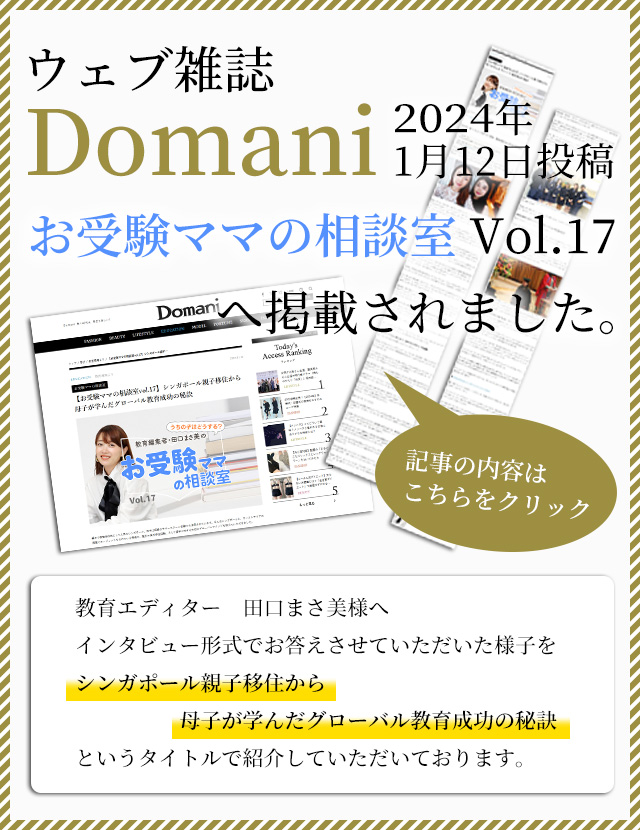【言葉を超えてつながった友情——母子留学が教えてくれたこと】
 国籍も文化も超えて——シンガポールで広がった娘の世界
国籍も文化も超えて——シンガポールで広がった娘の世界
こんにちは。AS Global Education 代表の岡 芳子です。
前回は、娘がインターナショナルスクールに通い始めてから、少しずつ環境に慣れていった日々についてお話ししました。今回は、そこからさらに一歩踏み込んで、多国籍な友人たちとの出会いや、文化を超えて育まれた人間関係について綴ってみたいと思います。
「話せない」から始まった友情
娘が最初に仲良くなった友人は、同じように英語が得意でないアジア系の女の子でした。
言葉がうまく通じない同士だったからこそ、目を見て笑うだけで分かり合えたり、身振り手振りで助け合ったり。
不思議なもので、“言葉が通じない”というハンデは、かえって心の距離を縮めてくれたのかもしれません。
少しずつ英語がわかるようになり始めた頃には、そこに中華系、インド系、ヨーロッパ系、アラブ系の友達も加わり、毎日のお昼の時間には、まるで世界の小さな縮図のようなグループができあがっていました。
文化の違いに戸惑いながらも、心で通じ合う
たとえば、日本では当たり前の「遠慮」や「空気を読む」といった習慣は、国によってまったく異なります。
言葉ひとつ、表情ひとつで、気まずくなったこともありました。
でも、そういうすれ違いも含めて、娘は「違う」ことを受け入れる力を育んでいったように思います。
「◯◯ちゃんはこう言ったけど、たぶん悪気はなかった」
「文化の違いかもしれないから、私ももう少し考えてみる」
そんな風に自分で考え、解釈し、柔軟に対応していく姿は、親の私から見ても大きな成長でした。
友情が娘を“世界の一員”にした
 ある日、娘が帰ってきてこう言ったんです。
ある日、娘が帰ってきてこう言ったんです。
「今日、友達の家で中華料理をごちそうになったの!初めての味もあったけど、すごく美味しくて楽しかった!」
それは中華系のお友達のご家庭に招かれての食事会だったそうです。
家庭ごとに異なる食文化や作法に自然に触れ、一緒に笑い合いながら食卓を囲む——それは単なる異文化体験ではなく、“受け入れ合う経験”だったのだと、娘の表情から感じました。
このような経験を重ねながら、娘の中には「日本人」としての自分だけでなく、「世界の中のひとり」としての自覚が芽生えていったように思います。
異文化の中で見えてきた“自分らしさ”
面白いことに、異文化の中に身を置くと、日本で当たり前だったことが当たり前じゃなくなります。
「ありがとう」や「ごめんなさい」の言い方も、目を合わせるタイミングも、全然違う。
でも、そうやって外の世界を知ることで、逆に“自分の軸”を持つことの大切さを娘は学びました。
「みんな違うけど、私は私でいていい」
そんな風に、自信をもって話す娘の姿を見て、私は胸が熱くなりました。
母としての喜びと、少しの寂しさ
友人関係が広がるにつれ、娘の世界はどんどん広く、深くなっていきました。
そしてそれは、親である私の手の届かない場所でもあります。
時には、話してくれないことも増えました。
それでも、帰宅して少し照れたように話す“今日あった嬉しいこと”や“友達と笑った瞬間”に、私はそっと耳を傾けていました。
母としては少しだけ寂しくもありますが、「自分の人生を、自分の足で歩いている」その姿を誇りに思っています。
最後に——“世界に触れる”ということ
シンガポールという国は、本当に特別な場所でした。
さまざまな背景を持つ人たちが、自然に共存している環境。
そんな中で娘が育んだ友情は、彼女の人格を形づくる大きな一部になっています。
私は今でも、あの時の決断が間違っていなかったことを、彼女の笑顔を見るたびに確信しています。
次回は、シンガポールでの生活リズムや食生活、そして現地で直面したカルチャーショックについて、お話ししたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が参考になったよ♪という方はシェアして頂けると嬉しいです^^